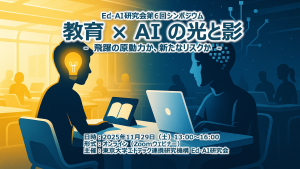Ed-AI研究会 令和7年度第1回Ed-AI WGの開催について
平素より、Ed-AI研究会の活動にご助力をいただき厚く御礼を申し上げます。下記のとおり、令和7年度第1回Ed-AI WGを開催いたします。
記
日時:2025年7月25日(金)17:00~18:30
形式:Zoomによるオンライン形式 (お申し込みはこちらからお願いします)
参加は無料ですが、会員以外の方は発言はできません。この機会にぜひ会員にご入会ください。ご入会はリンク記載のページからお願いします。入会方法
テーマ:「近年の大規模言語モデル(LLM)に関連する技術の進展と、その教育・学習場面における利用について」
講師: 東京大学 教授 越塚 登(Ed-AI研究会・会長)
本講演では、「近年の大規模言語モデル(LLM)に関連する技術の進展と、その教育・学習場面における利用について」というテーマのもと、急速に進化するAI技術、とりわけLLMとその発展型であるAI Agentの教育への応用について皆様と共に考え議論したいと思います。
近年のLLMは、自然言語処理を超えて高度な推論や専門知識の処理が可能となり、大学入試問題の解答やプログラム生成、さらにはタスク実行型の「エージェント」としての機能も備えつつあります。また、MCP(Model Context Protocol)やA2A(Agent-to-Agent)プロトコルによるコンポネント間連携が進めば、これまでと異なる機能が実現されます。
教育現場においては、LLMが学習者の質問に答える「伴走者」として機能することや、創造的活動の対話相手、あるいは個別最適化された学習支援の手段として期待されています。一方、一般的に言われる「AIを使いこなせる」ためには、当然一定の学力や知的訓練が前提です。したがって、それが習得されていない段階における教育への導入には慎重さが必要であることは言うまでもありません。そういう場面ではAIを単に「正解を与えるツール」として使うのではなく、「思考を促す補助線」としての使い方などが求められます。
例えば、産業分野ではすでに取り組まれているように、LLMはアイデアを広げたり、他者視点を取り入れたりするための対話(壁打ち)相手として有用です。また、学習者一人ひとりに合わせて説明や演習問題を生成することで、パーソナライズド教育の支援も見込まれます。教員の負担を軽減しながら、学習者の主体性を育むツールとして、LLMは多大な可能性を秘めています。
本WGでは、LLMやAI Agent時代における教育や学習のあり方について、課題と可能性の両面から皆さまと共に考え、議論する機会にしたいと思います。
以上